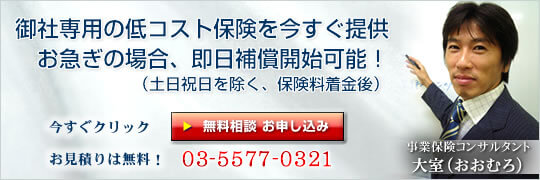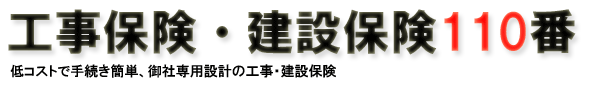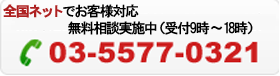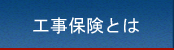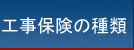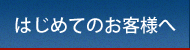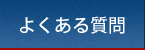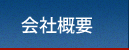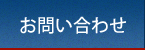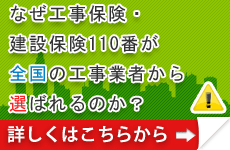政府労災の基礎知識
| このページは、皆様にご提案の任意労災保険とは別に、 政府労災保険の知識について、お役に立つよう作成した ものです。 本サイトの内容は執筆時点における法令および社会情勢に基づいて 記されています。 なお、利用者の経営結果については責を負いかねますので、ご了承ください。 詳細については、顧問社会保険労務士または最寄の労働基準監督署へ お問い合わせください。 |
||||||||||||
|
||||||||||||
| (2) 労災と補償制度 | ||||||||||||
①労働基準法-災害補償制度- 災害による被災労働者の救済制度は、労働者の生活保障 という面から極めて重要であり、各国ともこれを社会政策的 な意味で立法化している。 わが国においても、古くはエ場法(明治44年)の中に労働者や その遺族に対する扶助制度をとりいれたが、それが労働者災 害扶助法(昭和6年)となり、更に現在の労働基準法(昭和22年) の中の災害補償制度となってひきつがれている。 ②労働者災害補償保険法-補償責任の履行確保- 労基法上の使用者の災害補償責任は、法律上の義務として使 用者に対し罰則をもって強制されている。 その完全履行の裏付けとして、労働者災害補償保険法にもとづ いてつくられた保険制度が、政府労災保険である。 ③労基法をこえる政府労災保険 政府労災保険は、上述のとおり労基法に定める補償責任を履行 するための資力の裏づけとしてスタートしたものであるが、現在の 政府労災保険の給付内容は数次の改訂を経て、労基法に定める 補償内容より手厚いものになっている。 |
||||||||||||
| 2.政府労災保険の仕組み(保険関係) | ||||||||||||
● 政府(保険者)は、毎年、事業主等(保険加人者)から保険料を 徴収し、 ● 労働災害(業務上または通勤途上の災害)が発生した場合に、 被災労働者またはその遺族(受給権者)に対し、迅速公正な保険 給付を行う。 この仕組みを、保険関係という。 |
||||||||||||
| 3.適用事業 | ||||||||||||
(1)事業の概念 政府労災保険において事業とは、労働者を使用して行われる活動 をいい、企業という概念とは異なる。 工場、建設現場、商店等のように利潤を目的とする経済活動のみ ならず社会奉仕、宗教伝道等のごとく利潤を目的としない活動も含 まれる。 (2)強制適用事業と暫定任意適用事業 政府労災保険は、船員、公務員を除く民間事業のすべてを対象とし ており、原則として、労働者を1名でも使用している限り法律上当然 に、自動的に保険関係が成立する(強制適用)が、当分の間任意適 用事業とされているものもごく一部ある。 ①強制適用事業(およそすべての事業) 事業主は、特に保険加入手続を要せず、その事業の開始の日から 保険関係が当然に成立する。 →手続:事務手続上の要請により、保険関係成立の日から10日以内 に労働基準監督署(労基署)、または公共職業安定所(職安-労働 保険事務組合の場合)へ「保険関係成立届」を提出しなければならない。 ②暫定任意適用事業(下記の例外的事業) 事業主が保険加人の申請をし、政府の認可があったときに保険関係 が成立する。 なお労働者の過半が希望する場合には、事業主は加入申請をしなけ ればならない。 →手続: 「任意加人申請書」を労基署へ提出する。 →次の2つに該当する常時使用労働者4名以下の個人企業 ・土地の耕作もしくは開発または植物の栽植、栽培、採取もしくは 伐採の事業その他農林の事業。ただし、農業の事業のうち、その 事業主がその事業について特別加入している場合を除く。 ・動物の飼育または水産動植物の採捕もしくは養殖の事業その他 畜産、養蚕または水産の事業。 |
||||||||||||
| 4.適用単位としての事業(場) | ||||||||||||
(1) 事業(場)単位適用の原則 労災保険法は、個々の事業(場)毎に適用される。 即ち、個々の事業(場)毎に保険関係が成立し、事業の種類や労災 保険率が決定されるのである。 (2)継続事業と有期事業 一定の場所において、一定の組織の下に相関連して行われる作 業の一体は、原則として一の事業として取扱う。 ①継続事業 工場、鉱山、事務所等のごとく、事業の性質上事業の期間が一般 には予定し得ない事業を継続事業という。 ●継続事業における一つの事業(場) a.同一場所にあるものは分割することなく一の事業とし、場所的に 分離されているものは別個の事業として取扱う。(場所による決定) b.同一場所にあっても、その活動の場を明確に区別することができ、 経理、人事、経営等業務上の指揮監督を異にする部門があって、 活動組織上独立したものと認められる場合には、独立した事業と して取扱う。 C.場所的に独立しているものであっても、出張所、支所、事務所等 で労働者が少なく、組織的に直近の事業に対し独立性があるとは 言い難いものについては、直近の事業に包括して全体を一の事業 として取扱う。 ②有期事業 木材の伐採の事業、建物の建築の事業等事業の性質上一定の 目的を達するまでの間に限り活動を行う事業を有期事業という。 ●有期事業における一つの事業(場) a.当該一定の目的を達するために行われる作業の一体を一の 事業として取扱う。(目的による決定) b.国または地方公共団体等が発注する長期間にわたる工事で あって、予算上等の都合により予め分割して発注される工事に ついては、分割された各工事を一の事業として取扱う。 (注)1.一定の目的を達するために、場所的かつ時期的に相関連して行われる 附帯作業、迫加作業等は、一定の目的を達するために行われる事業の一部を なすものとして取扱われる。 2.時期的に独立して行われる作業であっても、当該作業が先行する事業に 付随して行われるものである場合には当該先行する事業に吸収して取扱われる。 (3) 複数事業(場)の一括 上記原則の例外として、以下の三つの場合には、複数の事業(場) を一括して一個の保険関係として処理し、保険事務処理の簡素化 を図ることが認められている。 ①継続事業の一括 経理事務を集中管理する事業が多い実情に合わせ、できるだけ 保険関係を一括して扱うようになっている。 一括の条件 以下のすべてに該当することが必要である。 a.事業主が同一であること b.それぞれの事業が継続事業であること c.それぞれの事業の種類が同一であること d.一括について政府の認可を得ること 申請の手続 「継続事業一括申請書」を労基署または職安へ提出する。 一括の効果 a.それぞれの事業場における保険関係は消滅し、指定を受けた 一つの事業場(一括された事務を扱う特定の事業場)において 単一の保険関係が成立する。 b.保険料納付事務は集中するが、保険給付事務は一括前の それぞれの事業場所在地の労基署が所管する。 ②有期事業の一括 小規模の有期事業を相前後して各地で行う事業主については、 一定の地域内で行われるそれらの事業を一括して一事業とみ なして保険事務を処理する。 一括の条件 a.事業主が同一人であること (注) 数次の請負による建設事業の場合には、労災保険法上 の事業主は原則として元請負人となるので(請負工事の一括)、 元請エ事のみが一括の対象となり、下請工事は一括の対象と することはできない。 b.それぞれの事業が、建設事業または立木伐採事業のいずれ か一方のみに属するものであること c.建設事業にあっては請負金額が19,000万円未満、立木伐採 事業にあっては素材の見込生産量が1,000㎥未満であること (注)ここでいう請負金額とは、請負契約上のものではなく、労災 保険料の算定基礎となる請負金額(工事用資材の価格や機械 器具の損料等を加減して算出した額)である。 d.それぞれの事業規模が、概算保険料の額で160万円未満で あること e.建設事業については、それぞれの事業の種類が同一であること f.それぞれの事業が、一定の地域内(保険料納付事務を扱う 事務所の所在地の都道府県内またはその隣接都道府県内) で行われること 申請の手続 不要 (上記条件をすべて満たすことにより、自動的に一括される) 一括の効果 一つの継続事業として取り扱われる。 ③請負事業の一括 発注者→元請負人→下請負人→再下請負人などのように、 2以上の事業が縦に請負契約によって連鎖される場合(数 次の請負事業)については、数人の事業主が存在することに なるが、通常相互に有機的関連があり、個別に保険関係を 成立させることは実情に合わないため、一括加入の途が開 かれている。 有期事業または継続事業の一括は、同一事業主が行ういく つかの事業を括したものだが、ここにいう数次の請負事業 の一括では、数人の事業主が数次の請負関係にたって行う いくつかの工事を一括し、元請負人のみを一括された事業 の事業主とするものである。 一括の対象 数次の請負による建設事業 申請の手続 不要 (左記条件を満たすことにより、自動的に一括される) 一括の効果 すべての工事が元請負人 の行う事業の一部と見な され、全体が一つの事業 として取扱われる。 ●下請事業の分離 当該連鎖の中の下請工事について、下請だけで請負金額が 19,000万円以上または概算保険料の額が160万円以上にな る場合には、元請負人は、「下請負人を事業主とする認可申 請書」を労基署へ提出し認可を得ることによって、その下請工 事部分につき独立の保険関係を成立させることができる。 |
||||||||||||
| 5.受給権者 | ||||||||||||
(1)労働者と遺族 政府労災保険の保険給付の受給権者は労働者であり、死亡 事故の場合はその遺族となる。 ①労働者 職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払わ れている者をいう(労基法第9条)。 従って、法律上の雇用契約の有無にかかわらず、事業に使 用されて賃金を得ている実態があればよい。 ②遺族 遺族への給付については、死亡者の収入により生計を維持 していた者について、次に掲げる受給資格者がいる場合は その人数に応じて年金で、いない場合は一時金で行われる。 生計を維持していたとは、主たる維持である必要はなく、一 部でも生計維持関係があればよい。 ●受給資格者およびその順位 ①妻 または 夫(60才以上または一定の障害の者) ②子(18才に達する日以後最初の3月31日まで、または一定の障害の者) ③父母(60才以上または一定の障害の者) ④孫(18才に達する日以後最初の3月31日まで、または一定の障害の者) ⑤祖父母(60才以上または一定の障害の者) ⑥兄弟姉妹(18才に達する日以後最初の3月31日まで、60才以上または一定の障害の者) ⑦55才以上60才未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹 上記①~⑦の資格者のうち最上位者に対し一括して年金 が給付される。 (注) 「一定の障害」とは、政府労災保険障害等級5級以上、 または傷病が治らず労働が高度制限を受けているかまた は労働について高度の制限を必要とする障害をいう。 ※給付額については、付5 政府労災保険・死亡(遺族補償 )給付明細表参照 (2)特別加入者 政府労災保険は、事業主に使用され賃金を受けている者の 災害に対する保護を主な目的とする制度であるから、事業 主、自営業者、家族従事者など労働者以外の災害は、本来 ならば保護の対象とはならない。 また、労災保険法の適用については属地主義により、日本 国内に限られており、海外の事業場に派遣された労働者の 災害は原則として政府労災保険の保護の対象とはならないとされる。 しかしながら、中小事業主、自営業者、家族従事者などの なかには、その業務や通勤の実態、災害発生状況等からみ て労働者に準じて保護するにふさわしい者がおり、また、海 外の事業場に派遣された労働者についても、外国の制度の 適用範囲や給付内容が十分でないために、わが国の政府労 災保険による保護が必要な者がいる。 そこでこれらの者に対しても、政府労災保険本来の建前を そこなわない範囲で政府労災保険の利用を認めようとする のが特別加入の制度である。 具体的には、①中小事業主等、②一人親方等、③海外派 遣者が対象となる。 ①第一種特別加人者(中小事業主等) a.中小事業主 常時使用する労働者数が300人以下の場合の事業主 (例外) 卸売・サービス業‥‥‥100人以下 金融・保険・不動産・小売業‥‥‥50人以下 b.中小事業主が行う事業に従事する役員・家族従事者 上記に該当する規模の従事者で、労働者にも、事業主にも該当しない者 法人企業の場合‥‥‥業務執行権のある役員 個人企業の場合‥‥‥事業主の家族従事者 →加入手続 ○条件 ・当該事業について保険関係が成立していること ・労働保険事務組合への保険事務の委託 ○手続 労働保険事務組合を通じて「特別加入申請書 (中小事業主等)」(記名式)を労基署へ提出し、承認を受ける。 労働保険事務組合 1. 制度のねらい 労働保険に関する事務の専任者をおけないような中小企業 に代わって、集団的に労働保険の事務処理を行う機関。これ に加入している事業主、個々の保険料額にかかわらず3分 割納付が認められる。 2. 形態 労働保険料の納付等労働保険に関する事務を、個々の事 業主に代わって処理することを認可された事業協同組合・ 商工会などの中小企業主の団体をいい、既存の団体であ っても差しつかえない。 3. 事務組合を利用できる条件 事業規模により制限されている。(金融・保険・不動産・小 売業では一企業全体で常時50人以下、卸売・サ一ビス業 では100人以下、その他では300人以下の労働者を使用 するもの。) 4.設立認可の方法 認可を受けようとする団体の主たる事務所の所在地を管 轄する公共職業安定所所長をとおして都道府県知事へ 届け出る。 5. 仕事の内容 適用事業の保険関係成立届の提出、暫定任意適用事 業の保険加入申請、保険料申告・納付、政府からの通 達のとりつぎなど 6. 政府の普及・促進措置 保険料納付率が合計の95%以上等一定の要件を充た すことにより報奨金制度の恩典があるほか、零細事業 被保険者福祉助成金制度が利用できるようになっている。 ②第二種特別加入者(一人親方等) a.一人親方その他の自営業者 労働者を使用しないで事業を行う、一人親方その他の 自営業者については、その仕事の危険の度合、業務 と私生活の区別の明確さといった観点から次の者に限り特別加入が認められている。 ・自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業 (個人タクシー、個人貨物運送等)を行う者 ・建設事業(大工、左官、とび、石工など)を行う者(いわゆる一人親方) ・漁船による漁業を行う者 ・林業の事業を行う者 ・医薬品の配置販売事業を行う者 ・再生利用廃棄物収集運搬事業を行う者 b.一人親方その他の自営業者が行う事業に従事する者 普通は家族従事者をさす。 C.特定作業従事者 ・特定農作業従事者 一定規模の事業場における危険性の高い農作業に従事する者 ・指定農業機械作業従事者 危険性の高い機械を使用する農作業に従事する者 ・職場適応訓練受講者 中高年齢失業者等休職手帳保持者で、国などが実施する訓練 作業に従事している者 ・一定の危険有害作業に従事している家内労働者とその補助者 例:機械によるプレス・型抜・研削作業や有機溶剤を使用する靴 鞄製造作業 ・労働組合の常勤役員であって一定の作業に従事する者(労組の 一人専従者) →加人手続 ・条件 同業者等の団体に加入すること(個々人でなくそれぞれの 属する団体が加入の単位となるため) ・手続 団体が「特別加入申請書(一人親方等)」(記名式)を労基署 へ提出し、承認を受ける。 ③第三種特別加入者(海外派遣者) a.開発途上国に対する技術協力実施団体(国際協カ事業団など) から海外に派遣される者 b.海外の事業に従事するため派遣(単なる出張は除く)される者 c.海外の中小事業の代表者等として派遣される者 海外出張者、海外派遣者の区分 海外出張者:単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内 の事業場に所属し、当該(国内) 事業場の使用者の指揮に従って勤務する者 海外派遣者:海外の事業場に所属して、当該(海外)事業場の使用 者の指揮に従って勤務する者 (注) 単に企業内でどのような扱いになっているかで区別するの ではなく、国内事業場に所属するか、海外事業場に所属するかの 実体的判断を伴うため、判断が困難な場合もある。 一般的には次表により取扱われる。 業務内容 ①商談のため ②技術・仕様等打合せのため ③市場調査・会議のため ④視察・見学のため ⑤現地での突発的なトラブル(製品事故・ 災害等)対策のため ⑥調整員(アフターサービス) ⑦海外留学(大学の研究室等) ⑧技術修得 ⑨海外駐在員 ⑩海外関係会社への出向 〔海外で行う据付工事(有期事業)の場合〕 ①総括管理者 ②指導員 イ.監督・指導のみ 口.自らも作業する場合 ③安全衛生指導員 ④事務員 ⑤一般作業者 ⑥現地で採用した者 取扱い 出張 特別加入 非適用 (注)1. 既に派遣されている者も特別加入が可能である。 2. 派遣者であっても、労働者の性格を有しない派遣先事業 (大規模事業のみ)の代表者となる者(現地法人の社長)や 留学生としての派遣は除外される。 →加入手続 ○条件 派遣元の企業または団体について保険関係が成立し ていること ○手続 派遣元の団体または事業主が「特別加入申請書(海外 派遣者)」(記名式)を労基署に提出し、承認を受ける。 |
||||||||||||
| 6.労働災害 | ||||||||||||
(1)業務災害 ①定義 政府労災保険における「業務災害」とは、労働者が労働契約に 基づき、事業主の支配下にあること(業務遂行性)に伴う危険が 現実化したもの(業務起因性)と経験則上認められる災害をいう。 (労働省の行政解釈昭和50.12.25基収第1724号の2) ●「業務遂行性」とは・・・・・・ 労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態をいう。 ●「業務起因性」とは・・・・・・ 業務と災害との間に経験法則に照らして相当と認められるところの 客観的な因果関係が存在することをいう。 この両者の関係は「業務遂行性」が「業務起因性」の第一次の 判断基準をなすと考えられている。 従って「業務遂行性」がなければ「業務起因性」は成立しないが、 「業務遂行性」があれば必ず「業務起因性」が成立するわけではない。 ②業務遂行性が認められる主な場合 ・所定の就業時間中に所定の就業場所で作業中 ・作業中の関連行為・付随行為中 ・作業の準備・後始末中、待機中 ・休憩時間中に事業場施設内で行動中 ・天災、火災等に際しての緊急行為中 ・出張途上 ・通勤途上で事業場の専用バスなど通勤専用交通機関を利用中 ③ 業務起因性の判断のポイント(負傷の場合) 「業務遂行性」の形態により「業務起因性」の判断は若干異なるが、 次の三つのケースに分類できる。
※具体的な認定事例については、付2 業務災害の認定事例 参照 は退勤のためになされること a.就業の場所と自宅との間の往復に、原則として毎週1回以上の
(3級)までの一時金が支給される。
c.通院費
・賃金額には現物給付を含むが、結婚手当などの特別な
|
||||||||||||