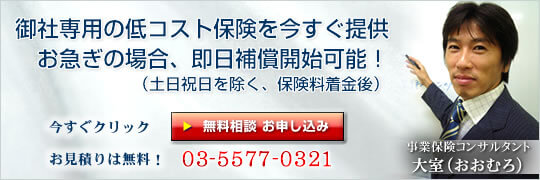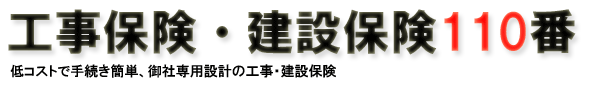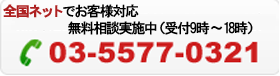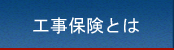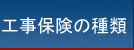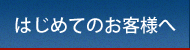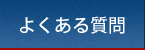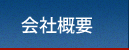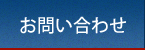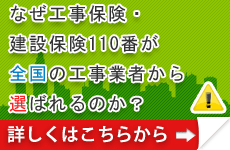個人事業主にとって工事保険とは
個人事業主として工事業務に携わる際、事故やトラブルに対する備えは重要です。
特に、個人事業主は法人と異なり、資本力が限られていることが多く、
予期せぬ事態が発生した場合のリスクを許容することが難しく、工事保険に
加入することでリスクヘッジを行うことがほとんどです。
この記事では、個人事業主が工事保険に加入すべき理由や、具体的なリスク管理、そして実際に保険を選ぶ際のポイントについて解説します。
1. 個人事業主の立場におけるリスクとは?
1.1 責任の全てを一人で背負うプレッシャー
個人事業主は、元請け業者があり、その元請け業者がすべての
責任を引き受けると明文化していなければ、有事の際に、事業主個人
が責任を負わなくてはならない危険性を常にはらんでいます。
また有限責任の法人と異なり、個人事業主は自らの事業について
全責任を負う必要があります。
例えば事業のために負った損害賠償金は、その個人自身の
損害賠償金と同じであり、仮に事業に失敗し、損害賠償金の
支払い原資がない場合、個人財産で支払いに応じなければなりません。
資金、労働力、リスク管理のすべてを一人で行う場合、
万が一のトラブルが発生した際の影響は非常に大きいです。
例えば、工事中に第三者にケガをさせてしまったり、物的損害を与えた
場合には、その賠償責任も自分自身で対応する必要があります。
1.2 大規模な資金の代替手段が少ない
個人事業主の場合、企業のように潤沢な内部留保や資金調達が難しいため、
トラブルが発生した際に自己資金だけで対応するのは現実的ではありません。
1.3 信頼の確保と競争力の向上
個人事業主が安定した顧客を獲得するためには、信頼性を築くことが重要です。
取引の条件として、工事保険加入を条件としている元請け業者が増えており、
最低限の責任・事務能力を持ち合わせていることの証左となっていることもあります。
保険に加入していることを示すことで、取引先や顧客に対して安心感を
与えることができます。
高額な工事やリスクの高い工事を請け負う際には、具体的な補償額を
満たしているか補償額・保険種類等の条件を提示して、その工事保険
証券の提出を取引条件として求める場合も増えています。
2. 個人事業主が工事保険を選ぶ際の注意点
2.1 自分の事業規模とリスクに合った保険選び
個人事業主でも、エアコンクリーニングや取り付け等、材料支給を受け、
手間作業のみを行う、工事用資材・設備をすべて仕入れ、一式を請け負う
場合もあり、内容や補償範囲は大きく異なります。
大規模な施設改修工事の場合は、引き渡しまでの工事目的物に対する
補償の優先順位が高くなりますが、材料支給され、手間で工事を受ける場合は
第三者への賠償責任保険が重視されることとなります。
自分の請け負う方法に応じて、過不足のない保険を選ぶことが重要です。
2.2 保険料と補償内容のバランス
保険料が高すぎると、事業運営に対する負担が大きくなる方、
安い保険では十分な補償を受けられないリスクがあります。
特に個人事業主は資金に限りがあるため、最適なバランスを
見つけることが求められます。
具体的には、起こる可能性はものすごく低いが、万一発生した場合、
人生が破綻するほどのインパクトがあるもの。
ここに保険を掛ける必要があります。
対人対物賠償は、事故内容により被害額は青天井となり、対人事故
の場合、賠償額が億を超えることも想定されます。
ここが最も優先順位が高い保険となります。
逆に自分の事業に最も頻繁に発生し得るリスクに補償を掛け、頻繁に
保険使用を行った場合、保険料の上昇や、契約更新の拒否など、
工事保険を利用できなくなる自体を引き起こします。
30万円の事故が起きても、人生は破綻しないかもしれませんが、
億の事故が起きた場合、生活が一変するのは目に見えています。
この時に保険に助けてもらうのです。
また、業務内容・請負内容に変更があるたびに、不要な特約・補償を
今一度吟味することが大切です。
例えば、工事の目的物・支給材料等の補償が必要なければ、プランの
ダウングレード・特約の削除で保険料を削減することができます。
2.3 むやみに免責金額【自己負担額】を高額に設定しない
保険契約には、事故が発生した際の免責金額「自己負担額」を
設定することによって保険料を抑えることが可能です。
自動車保険等で保険料を抑えるために、よく利用される免責金額ですが、
工事保険の場合、勝手が異なります。
年間売上規模が大きく、保険料が高額となるケースに削減効果が
期待できますが、年間売上高が高額にならない場合、ほとんど保険料に
影響がないケースが多いです。
ほぼ保険料が変わらないのに、事故の際に自己負担を強いられるのは、
賢明ではありません。
むやみに免責金額を高額に設定するのは早計です。
試算の上、免責金額の設定を行うようにしましょう。
3.個人事業主に選ばれる工事保険の種類
3.1 総合賠償責任保険
・リフォーム工事中、誤って発注者の建物の壁や柱にキズをつけた。
工事の目的物【自社所有物】に掛ける保険で、
通常の労災保険は従業員を対象としていますが、個人事業主自身は誰かに
・塗装作業中、塗料飛散により、駐車中だった近隣の居住者の車を汚損した。
・水道管埋設作業中、ユンボによりに既設ガス管をあやまって破損した。
・キッチン取付工事後、配管締め付け方が緩かったため、2ケ月経ってから水漏れし階下へ被害。
・看板取付工事後、施工不良で看板が外れて通行人にケガをさせた。
工事中に発生する賠償責任リスクに対して補償を得ることができます。
請負金額が低くても、事故のケースによっては高額な賠償責任を負う可能性
があり、一回の事故でいままで積み上げてきた売り上げ相当が吹っ飛ぶ
可能性もあり、個人事業主にとって、優先順位が高い保険となります。
支給材損壊や、リース品等の借用財物の補償が必要な場合、となります。3.2建設工事保険・組立保険・土木工事保険
火災、台風、豪雨による土砂崩れ等、盗難等を補償する保険です。
高額な材料仕入れを伴う、リフォーム・新築工事等では必須となります。
逆に材料はすべて支給され、手間請け仕事をしているケースの場合、
優先順位が低くなります。
その場合は、支給材損壊を補償する特約を賠償責任保険に付帯する
ことで対応が可能となります。3.3 労災保険(特別加入)・上乗せ労災・任意労災保険
雇用される立場ではないため、通常の政府労災の対象とはならず、特別加入
制度を利用する形となります。
加入するには組合に加入し、保険料とは別に組合費用を支払う必要があります。
民間保険会社の上乗せ労災・任意労災は似たような機能を持ちますが、
対象者の名前の登録が不要な、無記名方式となりますので、どのような職人が
入っていても、煩雑な手続きが不要で、自動的に補償対象となります。
応援・アルバイト・下請け業者を使用して仕事をされる場合は、優先順位が
高い保険となります。
4. 最後に:個人事業主にとっての工事保険の重要性
特に、リスクを自分一人で背負う形となる個人事業主にとって、万が一の個人事業主として工事保険を活用することは、避けては通れないステップです。特に、リスクを自分一人で背負う形となる個人事業主にとって、万が一の事態
に備えて、 心の余裕を持って業務に集中することができます。
工事保険に加入することは、予期せぬトラブルに対する「防御策」であり、
同時に事業の成長を支える「信頼の証」でもあります。最適な保険を選び、リスク管理を徹底することで、個人事業主としての成功を手に入れましょう。